企業および組織においては、通信・ネットワーク・セキュリティなどの IT要素を理解・操作するスキル、ITリテラシーに関する教育は欠かせないものになっています。セキュリティ意識を高めてインターネットの危険性を理解して正しく利用する力、情報社会での行動に責任をもち、正しい情報を見極め安全に利用できる情報モラルといった、情報の活用能力を身に付けて社会生活を送ることが求められていきます。
このような能力はいまだ個人差があり、学生時代に専門分野を学んで身に付けている人、個人的に興味を持って学んだ人、業務で必要があり学んだ人、職場の情報セキュリティ教育で学んだ人もいれば、そうでない人もいるのが現状です。
筆者ももちろんですが、現在の働く世代の大半が過ごした学校での教育には、ITリテラシーに関する教育はありませんでした。そこで今回は、現在の ITリテラシー教育の状況について筆者なりに調べてみました。
子供を取り巻く ITの脅威
現代の子供たちは、生まれたときからインターネットやスマートデバイスが身近にある「デジタルネイティブ世代」といわれます。便利で魅力的な IT技術の恩恵を受ける一方で、さまざまなリスクにさらされています。SNSトラブル、サイバー犯罪、フェイク情報、健康への影響、などのさまざまなリスクが挙げられます。
警察庁の公開情報の「インターネット利用に係る子供の犯罪被害等の防止について」では、子供たちの IT関連の被害および被疑の状況が報告されています。
この資料にある「【SNSに起因する事犯】学職別の被害児童数の推移」では、SNSに起因する事犯の被害児童数はおおむね横ばい状態であり、依然として高い水準で推移している、と報告されています。また、「【SNSに起因する事犯】罪種別の被害児童数の推移」を見ると、被害者の大半を中高生が占めていることがわかります。
公開資料は令和4年までの情報がベースとなっていますが、直近の情報では、連日ニュースを騒がせている、特殊詐欺/闇バイトといった事案が増えてきていますので、状況としては悪い方向に進んでいるでしょう。
新しい事案は次々に現れてくるため、後追いで対応していくしかないのが現状ですが、家庭・学習の場・社会が協力して、安全な IT環境を整備していくことが重要です。その中でも学習の場においての取り組みについて見ていきます。
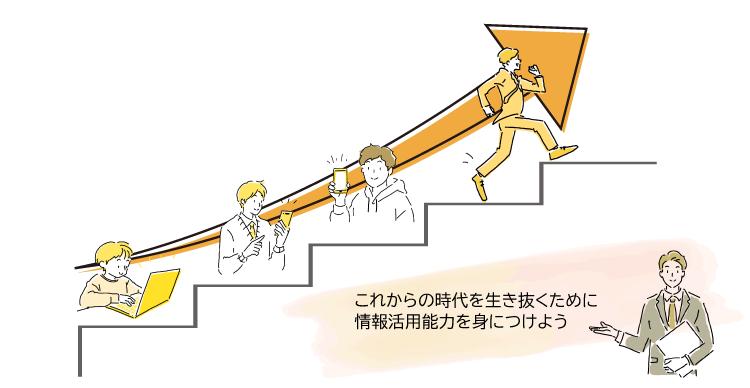
学習の場における ITリテラシー教育のこれまで
ITリテラシーに関する教育は、コンピュータ学習の一部として30年以上前から始まり、徐々に発展を続けながら現在ではプログラミング教育の一部として実施されています。年代ごとの主な内容は以下のようになっています。
初期の IT教育(1990年代~2000年代初頭)
1990年代後半からコンピュータやインターネットの普及に伴い、一部の学校でコンピュータの基本操作やタイピング練習などが導入される。
2003年度の学習指導要領改訂で、一部の高校に「情報」科が新設され「情報A・B・C」の科目で ITの基礎やプログラミングを学ぶようになる。
義務教育での本格的な導入(2010年代~2020年代)
2011年度の学習指導要領改訂で、中学校「技術・家庭」にプログラミング教育が追加される。
新学習指導要領により2020年度から小学校で「プログラミング教育」が必修化される。
→ ITリテラシーを含む教育が本格的にスタートする。
新学習指導要領により2022年度から高校「情報Ⅰ」が必修化される。
→ これにより、全ての高校生が ITリテラシーやプログラミングを学ぶ。
今後の展望
2025年度から大学入学共通テストに「情報Ⅰ」が追加される。
初期の時代は、学校による設備の有無や専門スキルをもつ教員の有無といった格差が課題であったといわれています。小学校でのコンピュータ学習 → 中学校での総合学習、と授業時間数の割り当てについても次第に増えてきているものと思われます。ITリテラシーの授業が義務教育で本格的に始まったのは、2020年度の小学校プログラミング必修化が大きな転換点です。その後、2022年度から高校「情報Ⅰ」が必修科目となり、より体系的な IT教育が行われるようになってきています。
「情報Ⅰ」が高等学校の必修科目として2022年度から追加されたのは、科目の整理を除くと当時の「情報処理(保健体育/家庭などの前身)」以来、40年振りとなります。

「情報Ⅰ」を代表とする新学習指導要領による ITリテラシー教育について
次に、新学習指導要領の策定に向けた資料「新学習指導要領について」について見てみます。
情報活用能力の育成について、小・中・高等学校別のポイントにまとめられている内容から、小学校においては、基本的な操作を習得する他、新たにプログラミング的思考を身に付けることが加わっています。ここでは、実際のプログラミングを体験しながらコンピュータに意図した処理を行わせるために論理的思考力が必要となっており、論理的思考といった観点の学習活動が計画的に実施されています。
中学校での対応として「プログラミング、情報セキュリティに関する内容を充実」とあります。これは、先の警察庁の資料にあった中高生のSNS事案の被害数が多いことへ対応するかたちで、情報セキュリティに関する内容の充実につながっていると思われます。
高等学校においては、情報科において共通必履修科目「情報Ⅰ」を新設し、全生徒がプログラミングや情報セキュリティを含むネットワークやデータベースの基礎等について学習します。
新しい必修科目「情報Ⅰ」で具体的に学習する内容の解説については、文部科学省の資料「高等学校学習指導要領(平成30年告示)解説 情報編」にて公開されています。200ページ近い内容です。ご興味がある方は一読いただければと思います。
高等学校では情報Ⅰの授業を毎週2時限学びます。
情報Ⅰとしてさまざまな科目がありますが、情報セキュリティ/情報モラルなどがありますので、ITリテラシーについても授業を通して身に付けていくことができます。
まとめ
今回、学校教育における ITリテラシー教育について調べてみました。
日本は諸外国と比べて対応が遅れているとも言われていますが、小・中・高等学校でのプログラミング教育が必修となった目的には、現代の子供たちがこれからの時代を生き抜くために、情報や情報技術を主体的に活用できる力=情報活用能力を身に付けられるようにすることです。
これからの社会全体のDX(デジタルトランスフォーメーション)に適応するためにも、ITリテラシーの向上は欠かせません。
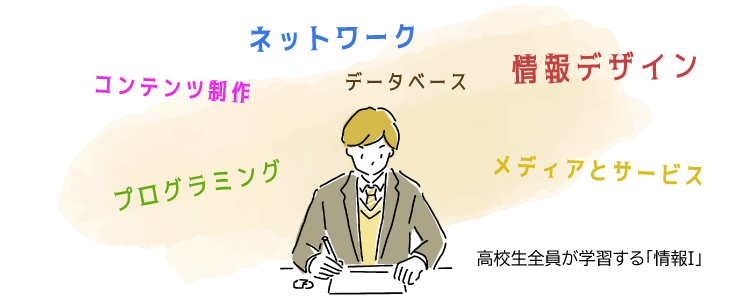
小・中・高等学校の授業で IT関連の学習ができることは非常にいいことだと思います。私も IT業界で20年以上勤務していますが、大学では半導体を専攻していたため、ITは働き始めてからの学習でした。新学習指導要領を完走した現代の子供たちとは IT知識の定着度が大違いだと思われますので羨ましい限りです。
我が家の子供から受けた印象で、タバコが健康に与える影響についての意識が高いと感じたことがあります。おそらく、学校での授業の一部であったり、何らかの取り組みから受けたものなのだろうと感じていました。
これと同じようなかたちで、ITリテラシーについても子供のうちから浸透していくといい方向に作用することもあるのだろうと思います。
※記載の製品名は、各社の商標または登録商標です。


